【PROto】どこを見る?どう考える?患者急変時のアセスメント実践編 Part2
記事執筆:
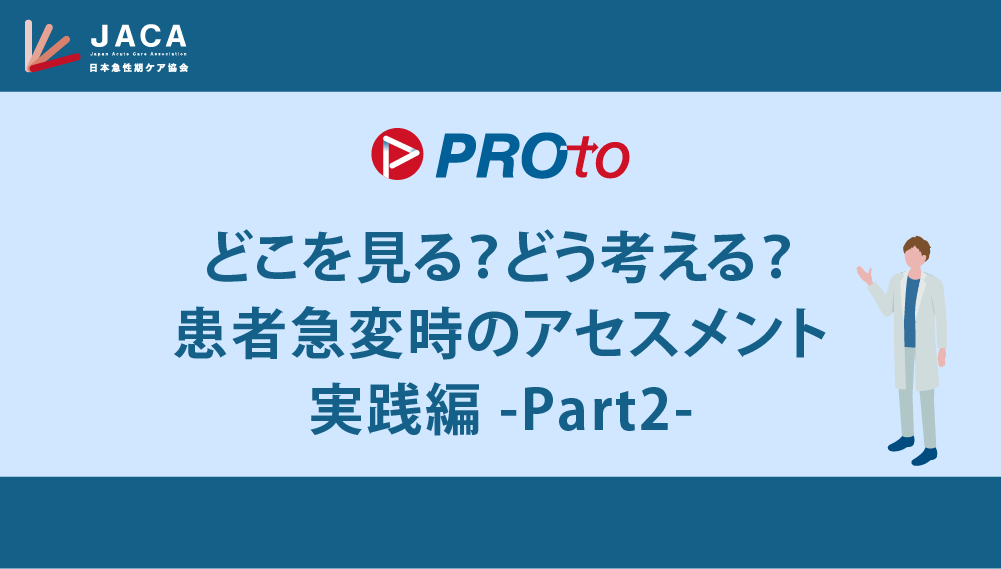
- 目次
~2026年4月20日まで
2026年5月8日~5月24日
今回は、2025年5月30日に開催された、PROto「どこを見る?どう考える?患者急変時のアセスメント実践編」セミナーに参加していただいたみなさんの質問にお答えしていきます。

回答者
日本急性期ケア協会 アドバイザー
救急看護認定看護師
杉松 幸太郎
株式会社NEXAS 代表取締役
メディケア訪問看護リハビリステーション福岡南 管理責任者
救急看護認定看護師
末永 一祝
参加者からのご質問と回答の紹介
Q.どの場面でどのツールを使うのか?今一理解できてないです。時間切迫下で、速やかに利用するために工夫してることがありましたら、教えて欲しいです。
末永
A. ツールやスケールは「何を評価したいか」「どの段階か」に応じて使い分けています。ツールは判断を助ける補助です。切迫した状況に限らず、まずは普段からABCDEの流れに沿ってツールを組み込み使っています。そして、判断の結果がどうだったかの検証を繰り返しやっています。
杉松
A. どの場面ということはありません、患者を観る上で1番大切な事は生命兆候であるABCDEを観ることです。もちろん意識障害で発見したら、BCをチェックして一次救命処置の流れに入りますが、CPAでなかった場合はABCDEアプローチに入っていきます。速やかに実施するためには、普段から急変していない患者に対しても意識をしてABCDEを観るということが必要かと思います。あと、すぐに応援を呼んで手分けして評価したり、処置の準備をしたりすることかと思います。
Q.部分的な痙攣がではじめたのか不随運動があるのか、新しい患者だと迷うことがあります。肺雑音も、耳の調子が悪くなり違いをイメージしにくいです。文字では理解できても、現場で判断迷ってしまうのではダメですよね。何かコツがあれば、ご教授願います。
末永
A.不随意運動は持続的・反復的で、運動のリズムや部位が安定していることが多いです。部分発作であれば中枢性の兆候を伴うことがありますので、意識と合わせた観察も重要です。
また、発症様式や過去の情報(発作は初発?過去もあった?など)を聴取することも重要です。耳の調子が悪く聴診が難しければ、触診・打診などその他のスキルも大事なのでそこを高めても良いかもしれません。
杉松
A.意識障害や眼球上転していた場合は痙攣の可能性が高くなります。中には意識障害を伴わない痙攣もあるのでその点は注意が必要です。また、痙攣の既往があることも判断材料になると思います。
肺雑音聴取ですが、私の場合は連続性か断続性かを評価します、その後に吸気と呼気または両方の時に聞こえるかを評価します。その流れで聴診することで、分類を絞ることができます。最終的にこれだ、と思った音が患者状態とマッチするのか、も考えています。
Q.訪問でこの専門士をどう活かされていますか。
末永
A.臨床判断に活かしています。また、医師や救急救命士また救急病院への連携、繋ぐ場面で双方の役割や環境を学習していることで治療や搬送になった場合、橋渡しのアプローチも幅広くなりました。
Q.第一印象と一次評価を混同してしまうことが多く、どういう風に指導すればいいでしょうか。
末永
A.簡単で分かりやすく表現すると第一印象は感じる→一次評価で理由を探るでしょうか。第一印象から口頭で言語化させ、その後ABCDEで根拠づける演習が有効です。シミュレーションで全て言語化させてトレーニングさせる指導を実践しています。
杉松
A.簡単にいうと、ヤバイかどうかを一瞬(数秒)で観るのが第一印象、どこがヤバイのか、それに対してどのような処置を実施するべきか再評価するのが一次評価、と考えると指導しやすいのではないかと思います。
Q.呼吸窮迫時の酸素投与について、開始時の流量はどのように決まるのでしょうか?私は外来勤務のため、幸いにもすぐにドクターの指示をもらえますが、そうではない場合の対応を知りたいです。
末永
A.施設や在宅であれば、緊急時や突然の状態変化に備え事前に医師へ指示を確認しています。
杉松
A.明確に何リットルということはないかと思っています。動画配信B(呼吸)のスライドにあったように、患者の基礎疾患を考慮しながらSpO2の値によって酸素を増減することが良いと考えます。呼吸様式や呼吸回数の変化も観ていくことは大切です。
Q.今まで経験した症例で判断に迷った事や難しかった症例から学んだことを教えてほしいです。
末永
A.緊急度は低いが重症度が高い方など、今すぐの救急要請は必要ないが確実に治療はしないといけないことを見据えている場面は特に迷います。症状やその変化のスピード、利用者家族の精神的・危機的な状況、意思、そして自宅で療養できる環境か?など様々な要因を統合して判断や調整に繋げる難しさを今まさに学んでいます。
杉松
A.たくさんありすぎますが、その度に思う事は知識の重要性と過小評価しない事が重要と思います。知識の重要性は読んで字の如くですが、過小評価に関しては「まぁ大丈夫かな」「いつもあるしね」「今忙しいしこのくらいはいいかな」などのように、自分の都合で解釈した時に痛い目に遭ってきました。判断に迷ったらオーバートリアージする事で、大きなトラブルになることを避けられると考えています。また自分の評価を口に出すことで、周りと情報を共有することが大事です。そうすることで、「それは違うんじゃない」「こうすべきだろう」という意見をもらえ、複数のスタッフで評価できると考えます。
Q.自施設では医師の指示があるまで酸素投与が出来ないです。指示がない場合先ずは最初の酸素量はどれくらいから始めれば良いでしょうか?
末永
A.施設や在宅であれば、緊急時や突然の状態変化に備え医師へ事前指示を確認しています。ただ、指示を受けるのではなく、「この患者は今はこういう状態で今後、どのようなリスクがある」ことを踏まえて医師へ打診することがあります。それでも難しければ、施設内で急変を早期に察知するためのスクリーニングツールなどを取り入れてハード・ソフト面を強化しても良いかもしれません。
Q.日常の看護介入場面での観察で第一印象〜ABCDEアプローチを、意識して看護職員が行えるよう努めたいと思っています。その中でSpO₂値を優先する看護師が多いので、呼吸回数や呼吸様式の大事さを重視したいのですが、講義を行う中でどのような内容を盛り込むとよいかや資料作りのアドバイスを頂けると幸いです。
末永
A.講義設計で、なぜ呼吸回数は重要なのか?の根拠は必須かと思いますが、「同じSpO₂でも見た目が違う動画比較」、「SpO2:94%は正常か?」など現場でリアルな事例をいくつか提示して視覚からアプローチすると落とし込みやすいかと思います。また、自施設の過去に実際に起こった急変事例を遡り、急変の前兆に頻呼吸が起こっていた‼︎など統計やケースを示すことで、より学習者の動機づけにつながると思います。
杉松
A.比較するような話をするとわかりやすいと思います。例えばSpO2 95%という値を提示します。次に指導者である貴方が、落ち着いた呼吸ときつそうな呼吸をしてみせます。それぞれの呼吸様式と呼吸回数も数えさせます。そして、それぞれどのような処置をするか確認してみましょう。おそらくきつそうな呼吸では酸素投与や体位管理などの意見が出ると思います。そこでなぜそうしたのかを問うてみると理解してもらえるのではないかと思います。頑張って呼吸をしないと酸素化を維持できないのは異常であると思えるはずです。
急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。
状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。
また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。
もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。









