在宅看護における急変対応②(夜間オンコールの場合)
記事執筆:
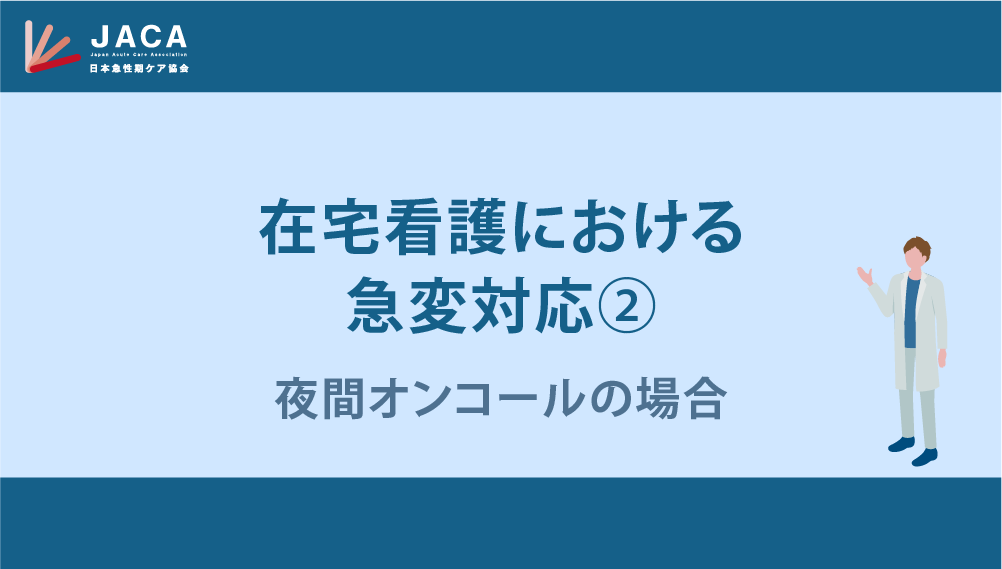
- 目次
~2026年4月20日まで
2026年5月8日~5月24日
事例紹介
人物紹介

80代 男性 悪性リンパ腫末期 糖尿病 慢性腎臓病(非透析)
悪性リンパ腫に対する治療を行っていたが、体力低下もみられ治療を中断し在宅療養中。
入院は絶対したくない、が口癖であり、家族も本人の意向を尊重したい、と話していた。
インスリンや内服薬は自己管理中、血糖値の記録もしっかり記載できている。
経緯
訪問当初は、生活動作はほぼ自立しており、1回/週の訪問頻度であった。「なんで、毎週、看護師が来るんや、元気やのに」と言えるほどであった。
半年経過した時点から、徐々に寝ている時間も増え、食事量の低下もみられていた。インスリンなども自己管理できていたが、低血糖も頻発しており、自己管理が難しくなっていた。妻と二人暮らしであったが、妻には軽度認知症があり、長女が介護休暇を取り、サポートしていた。
最近の体調の変化について、スタッフ間で情報共有を行い対応方法も話し合っていた。
ある夜、長女より連絡が入る。「昼食を食べた後ずっと寝ていて、夜ご飯も食べずに寝ていたので、声をかけたけれど目を開けません。息はしているけど、しっかり話ができないです。どうしたらいいですか?」と連絡があった。
状態把握
アセスメント
呼吸はしているが反応が薄い、昼食は食べている、寝ているような状態、等の情報と、ここ最近の低血糖の頻度を考え、電話越しに、長女に血糖の測定を依頼した。測定値は45mg/dL、と低血糖であったため、頭を起こして、窒息しないようにし、低血糖時に内服する砂糖を溶かして、舌の下に少しずつ流しながら、血糖値を上げるケアを依頼して緊急訪問に向かった。
訪問時、本人は、椅子に座り夕食を摂取できるほどに意識が回復していた。「おお、看護師さん、どないしたんや」と会話も成立していた。しかし、まだぼんやりしている。
〈バイタルサイン〉
・体温36.2℃、血圧100/66mmHg、脈拍70回/分、呼吸回数16回/分、SpO2 97%
・JCSⅠ-1、手足の麻痺や顔面麻痺はなし、舌のゆがみ無し、瞳孔不同なし、対光反射あり
・夕食はご飯茶碗半分、味噌汁、野菜の煮物などを摂取できている
対応
訪問に向かう際、本人が救急搬送を拒否する可能性が高いと判断し、自宅での対応として点滴投与の可能性も考え、在宅医から預かっていた点滴セットも持参して訪問した。
▼
▼
低血糖に関連した意識レベルの低下であったが、念のため麻痺の有無、言語障害や嚥下障害の有無など脳卒中の評価を行いつつ、経過を観察した。
▼
▼
ご家族から、本人の様子、朝からの食事量、飲水量、排泄量、血糖値の推移、内服状況も確認した。食事摂取後、30分以上経過した血糖を測定したが、100mg/dLと上昇の度合いが遅いことを確認してから、在宅医に電話で状態を報告した。
▼
▼
状態は改善し自宅での生活を継続できると判断、しかし、血糖値がやや低いため、ブドウ糖入りの点滴追加の指示あり。電話で医師から本人、家族にも説明してもらい実施する。
追加で医師に、最低限必要な薬やインスリンの中止など指示を確認した。
▼
▼
長女さんの判断により、父親の命が救われたことを労い、翌日の朝にも訪問する了承を得て退室した。
振り返り
ここ最近の本人の体調の変化について、スタッフ間で情報共有を行っていた。オンコールがかかってきそうな人をピックアップして、対応方法も話し合っていたため、判断に迷うこともなくスムーズに処置が行えた事例である。

入院はしたくない、という、本人の強い希望を叶えるために、在宅療養でできる最大限の治療は行えたと考える。
その後、数週間後に腎機能が急激に悪化し、本人が治療を望んだため入院することとなった。最期は自宅に戻り、数日間、家族と穏やかに過ごされ、眠るように息を引き取られた。
<参考文献>
一般社団法人日本急性期ケア協会
急性期ケア専門士 公式テキスト
全国在宅医療マネジメント協会
在宅看護指導士 公式テキスト
急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。
状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。
また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。
もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。









