急性期で必要とされる認知症看護 Part2
記事執筆:
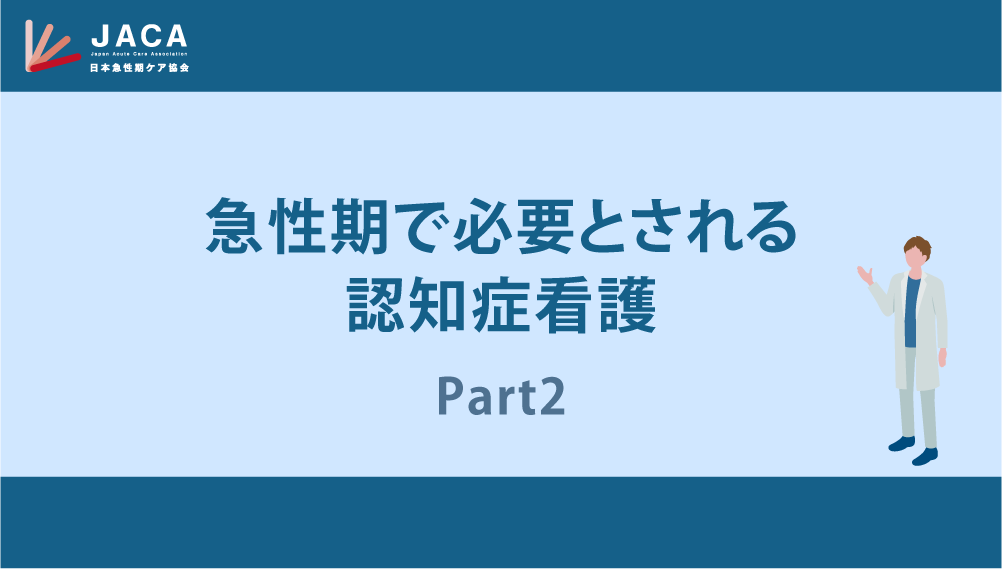
- 目次
~2026年4月20日まで
2026年5月8日~5月24日
救急外来での対応
救急外来での認知症患者さんの様子
認知症の患者さんが救急車で搬送されてきた場合、医療者としては「1秒でも早く、治療や検査の準備を進めていきたい」と矢継ぎ早に説明してしまいがちです。しかし、本人は何が起こっているか、どうなっているかは理解できていないことが多く、恐怖・不安・体調不良などが重なり、興奮している場合があります。

このような場合どのように対処すれば、安心してかつ安全に検査を受けてもらえるでしょうか?
救急外来での対応
私たち医療従事者は、マスク・エプロン・ゴーグル・手袋などを装着して対応することも多く、認知症の患者さんにとっては、知らない人に囲まれるというとても怖い状況になります。認知症の患者さんがどのようなことに不安や恐怖を感じるのかを理解し、安心できる対応をすることがスムーズな診療につながります。
急性期に必要とされる認知症看護実践能力
実際に、急性期で必要とされる認知症看護としては下記の点に留意します。
- 認知症患者の認知機能・身体・心理状態を正確に把握する
- 認知機能の低下がある人が安心できるコミュニケーションを図る
- 尊厳を意識し、尊重する
- 生活史や思考・言動から患者を理解し、個別性のあるケアを行う
- 余裕をもってケアを行うためのセルフマネジメントをする
難聴があるからと、耳元で大きな声で話すだけでなく、声のトーンや伝える言葉の使い方まで気にしていますか?
分かりやすく伝えるにはどうすればいいかを考えましょう。認知症があるなしに関わらず、混乱している人に対しての関わり方の基本となるはずです。私たちのイライラした気持ち、焦っている気持ちは相手に伝わってしまいます。
効果的なかかわり方
認知症の行動・心理症状の予防や緩和には、次の3つが有効と言われています。
- ①身体的不調へのアプローチ
- ②環境変化による混乱を最小限にした安心できる環境づくり
- ③不安や恐怖を軽減するための安心できるかかわり
急性期病棟での対応
さて、認知症の患者さんが外科の手術後で、ドレーンや点滴、尿道カテーテルが挿入され、痛みもあり、モニターも装着されている場合を考えてみましょう。

ドレーンを自己抜去されてから対処するのではなく、術前の様子と比較して観察を行います。
「手術前より表情が険しいな」
「不安な言動が多いな」
「痛みのコントロールが不十分だな」
「何度も、チューブを触って確かめているし、何度も同じ質問をしているな」
など、関わるスタッフで情報共有を行い、何パターンもの先回りしたケアを考えておくことが大切です。
入院中を安全安楽に過ごすための対策
- BPSDが出ている原因や症状に合わせて、適切なケアを行う
- 安心して過ごせるよう環境を調整する
- 認知機能の低下に合わせて安全対策を行う
認知症の患者さんは、痛みを適切に伝えることができず鎮痛薬が足りていなかったという場合もあります。術前の様子との比較、体動・咳嗽・呼吸などから適切に鎮痛ができているかを確認することが重要です。
術後は、痛みのコントロール、チューブ類の整え方、適切な薬剤でのコントロールが必要となります。適切なタイミングで投与するには、やはり本人の様子を細かく観察しておくことが大事になります。普段の様子と何が違うか、多職種で協力しながらケアのバトンを繋いでいきましょう。
かかわり方のポイント・声かけ
離床センサーが反応してから訪室するのではなく、頻回に顔を見に行き、声をかけることが大切です。
「お腹の痛みはどうですか」
「この点滴は、今、痛みを和らげるのに必要ですので、そのままで大丈夫です」
など、先回りの声掛けや意識付けを行いましょう。
声をかけるだけでは難しい場合は、簡単な文章を書いて、本人が見えるところに置くなどの工夫もいいかもしれません。
さいごに
イライラした気持ちは、雰囲気などで患者さん本人に伝わってしまいます。
そうならないためにも、医療従事者側がケアの引き出しをより多く持つことが大切です。患者さんがどんな行動を取ったとしても、「そのパターンで来ましたか!予想範囲内!」と言えるくらい、心に余裕が持てるよう、普段から予測しておくことが大切となります。
<参考文献>
終末期ケア専門士 公式テキスト|第2版
一般社団法人 日本終末期ケア協会急性期ケア専門士 公式テキスト|第1版
一般社団法人 日本急性期ケア協会急性期病院で必要とされる認知症看護実践能力|J. Jpn. Acad. Nurs. Sci. 40: 448–456 (2020)
浦島尚子他/blockquote>
同じく急性期領域における認知症看護は、こちらのブログもぜひご覧ください。
認知症の種類やBPSDについて説明しております。
急性期で必要とされる認知症看護 Part1
急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。
状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。
また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。
もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。









